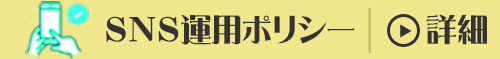アーカイブ
熊本地震への支援 ~被災地外から被災地へ~
![]()
先月14日夜、大きな揺れを感じて、咄嗟にテーブルの下へ。北九州市でも震度3。翌日の夜中にまた、携帯の「地震です、地震です」で飛び起きて一晩中、テレビにかじりついて地震情報を見て過ごしました。
被害は熊本から大分まで広がり、南阿蘇の友人を訪ねたときに通った阿蘇大橋まで崩落。大変心が痛みます。被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
昨年4月の所長ブログでご紹介しましたが、全国女性会館協議会が中心になって「大規模災害時における男女共同参画センター相互支援システム」を構築し、インターネット上に情報プラットホームを立ち上げています。

今回の熊本地震では、災害発生の翌朝からインターネット上で情報共有・交換がスタートしました。
多くのセンターから被災地のセンターへ、お見舞いと協力の申出、支援物資が送られています。
その中で、全国女性会館協議会では、会員館からの義援金をプールして一本化し、被災地の男女/女性センターにお届けすることにしました。ムーブ、レディスもじ、レディスやはたでもその呼びかけに呼応し、先月22日から窓口に募金箱を設置しています。皆さまのご協力をお願いいたします。
また、インターネット上の情報交換の場を利用して、
・新潟県の中越地震・中越沖地震の際の経験から、避難所でのプライバシーの確保やルールづくり、運営には必ず女性のリーダー格の人を入れること。
・東日本大震災の経験から、センター職員も被災者であり、被災地のセンター自身が「やろう」と思えることだけを、自分たちのペースで実施すること
など、貴重なアドバイスが送られています。
このような中、現在“熊本市男女共同参画センター・はあもにい”では、
◆女性や子どもへの暴力防止の啓発ちらしの避難所での配布
◆オフィスでの業務が困難という方のための、サテライトオフィスの設置
◆ちょっと、家や避難所から離れホットされたいお子様お持ちの保護者の方への幼児室の開放
などに取り組まれています。
まだまだ余震が続き安心はできませんが、支援もその時々の被災地の状況に合わせた支援が必要になると思います。全国の男女/女性センターとも協力しながら、ムーブでもできることがあれば支援してまいりたいと思っています。

『ただいま、女性活躍中!これからの実践手引き』を発刊しました。

28年度がスタートしました。
27年度末をもって去られたスタッフの方々は、多くの実績を残していかれました。そして、新たに来られたスタッフは、ムーブに新しい風を吹かせてくれることでしょう。
さて、私も、ムーブ所長4年目に入ります。開かれたムーブを目指して、皆さまに楽しくご利用いただけるよう努めてまいります。
さて、今日は、昨年度末に完成した『ただいま、女性活躍中!これからの実践手引き』をご紹介します。
ムーブでは、平成26年度に「北九州市における女性の活躍推進実態調査」を行いました。この実態調査は、女性の活躍推進を加速していくために、市内の事業所で女性の活躍に関して、どのような取り組みが行われているのか、その実態を明らかにしようと実施したものです。
その結果、女性活躍推進の取り組みについて、半数近くの事業所が取り組みを行うことにしているとの回答がありました。しかし、「今のところ取り組む予定はない」という事業所が約半数で、事業所間で格差がありました。この結果を受けて、平成27年度は、女性活躍推進の進め方のヒントとなる先進企業の取り組みを紹介した冊子を作成することにしました。
その冊子が『ただいま、女性活躍中!これからの実践手引き』です。
読めばわかる、今すぐにでも取り組める、女性の活躍推進の好事例集です。各企業が女性活躍推進の取り組みに当たって、マニュアルとして使えるようになっています。
経営者、人事担当者、管理職、女性社員自身のそれぞれの立場からの取り組みを紹介しています。
例えば、
人事担当者編として、
Q 何から手をつければよいのでしょうか?
A 専門部署を設け、数値目標と中長期行動計画を策定した、北九州市役所の事例
管理職編として
Q 女性社員の自律的なキャリア形成を支援する方法とは?
A 先輩が若手社員の相談に応じる「メンター制度」を導入した、西部ガス北九州支社の事例など11社の事例を紹介しています。
また、女性の力を商品開発などの新たな価値創造に上手につなげた先進事例として株式会社ごとう醤油など3社を紹介しています。
この冊子には、各社が女性活躍推進の一歩を踏み出す多くのヒントが示されています。ぜひ、ご活用いただきたいと思います。
ご希望の方はムーブまでご連絡ください。
.png)
小倉昭和館 3代目館主 樋口智巳さん

2月13日(土)は、ムーブ・レディス映画祭、ムーブとレディスやはた、レディスもじの3館連携事業で、昨年に引き続いての映画祭でした。今年度は「前向きに生きる女性の姿」がテーマ。ムーブは『ミス・ポター』、レディスもじは『くじけないで』、レディスやはたは『折り梅』。どの映画もたくさんの方々に参加していただき大好評でした。
ムーブでは、上映に先立ち、小倉昭和館の館主 樋口智巳(ひぐちともみ)さんにお話をしていただきました。
今回は、3代目として、小倉昭和館を守ろうと奮闘する樋口さんのことや小倉昭和館のことをご紹介したいと思います。
小倉昭和館は、1939年、芝居小屋として開館し、今年で創業77周年。娯楽のない時代に「人々の喜ぶ顔が見たい」と樋口さんの祖父が始めました。片岡千恵蔵、阪東妻三郎、長谷川一夫など多くの役者さんと親交があり、特に片岡千恵蔵さんとは親友のような間柄で、1953年の北九州大水害の時には、心配した京都の千恵蔵さんから電話があり、状況を聞いた千恵蔵さんは「今から四条河原町に行って街頭で北九州の為に募金活動をする。」と言って、本当にしてくださったそうです。
戦後、芝居小屋から映画館に改装し、1955~1960年頃の映画全盛期には、小倉昭和館のほかに日活館、松竹富士館、木町東映の4つの映画館を運営するように。富士館を除く3館の合計で1日1万人のお客様が押し寄せた日もあり、金庫も満杯で鑑賞料のお金を一斗缶に詰め込んで保管したこともあったということです。
しかし、時は流れ、映画は斜陽の時代に。小倉昭和館以外の3館は閉館、昭和館も半分をパチンコ店に改装。その後、1982年にはパチンコ店を辞めて「小倉昭和館1号館、2号館」体制に改装し、子ども向けアニメのヒット等で何とか経営を継続。
近年は、シネコンの台頭で2003年には昭和館以外、北九州市内の映画館は全てシネコンになっていきました。このような厳しい環境の中、小倉昭和館は独自の路線で運営。シネコンと同じタイミングで同じ新作を上映しても太刀打ちできません。2本立てにこだわり、シネコンが上映しなかった作品「北九州初公開」の作品を積極的に上映しているということです。
映画館は十数年間赤字で、他の部門の利益の補填でなんとか運営しているという状況。「映画館は”家業”守っていきたいと思っている。」その気持ちを決定づけたのが、高倉健さんからの手紙でした。健さんの遺作『あなたへ』にエキストラ出演した際に、小倉昭和館でも高倉健特集を行っていたことをご存知で、「私の映画を上映してくれてありがとうございます。」と言って握手をしてくださった。
その後、健さんにお目にかかれたお礼と、映画館を継続させるかどうか悩んでいるとお手紙すると、健さんからのお返事がきました。「現実は厳しいと思いますが、どうぞ日々生かされている感謝を忘れず、自分に嘘なく生きてください」と…。その手紙でこのまま映画館を続けようと、決意を新たにされました。
お客さんに楽しんでもらえるにはどうすればよいのか。上映作品の監督や原作者、出演者の方々のシネマトークや舞台挨拶を企画したり、上映作品にちなんだ食品を販売しています。コーヒー焙煎世界大会優勝者の協力で小倉昭和館オリジナルブレンドコーヒーも製作販売しました。
また、西鉄バス、清張記念館、北九州市立文学館など、さまざまな団体とのコラボレーションも積極的に展開。北九州マラソンにちなんだ映画やマラソンランナーのトークショーなど斬新な企画は尽きず、館主樋口さんの小倉昭和館から目を離せません。
劇場のレンタルや、デートで貸切なんてこともできるそうです。
映画好きの私としては、もっと書きたいのですが、今回はこれまでです。

『私がわたしのベストフレンド』を開催して

今年のムーブ事業のスタートは、1月9日の『私がわたしのベストフレンド~自分を最高のパートナーにするために~』でした。
ちょっと落ち込んだり、気持ちがコントロールできない方に、「少しでも前向きになっていただきたい」と開催した講座です。驚くことに、市政だよりに掲載後、あっという間に定員を超える申し込みがありました。この反響には、少し驚きです。
このような講座は初めてなので、まずは参加しやすいように、コンパクトにまとめて2時間半の講座にしました。
途中にワークを挟みながら実施。ワークについては、講師からは、気が乗らないときや、思い出したくない事を思い出しそうなときは参加しなくてもよい、無理をしないようにとの配慮がありました。私も参加しましたが、ゆるやかな、癒される時間を過ごすことができました。
内容は、「フォーカシング事始め」「健在意識と潜在意識」「アサーション」など、各自が持ち帰って、自分自身をエンパワーメントすることができる方法も、少し触れてくださいました。
受講された方からは、
「自分の内側をしっかりみつめて自分の心の声を聴き、前向きに過ごしていきたいと改めて感じることができた。」
「自分をコントロールできずに困るときがあり参加したが、大変参考になった」
「7年間ずっと引きずっていたイヤな記憶を、びっくりするほどあっさりポイすることができた。」など、
「元気になれた、来てよかった」と良い評価をたくさんいただきました。
他の相談機関でも「心を病んでいる人からの相談を多く受けている。相談室として、心の病になる前にできることは無いのだろうか」ということが話題になっています。
ムーブ相談室でも同じ思いでこの講座を企画しました。落ち込んだとき、自分自身を取り戻してほしいとの思いが実った講座です。今後のムーブの新しい分野を切り開くプログラムになりそうです。
早速、新年度に向けて企画をしていますので、また、ご参加くださいね。

明けまして、おめでとうございます。

明けまして、おめでとうございます。
早いもので、平成25年4月にムーブ所長に就任して3年が経とうとしています。昨年はムーブ開所20周年記念事業を実施し、ムーブの利用者も600万人を超えました。
さらに、平成28年度から5年間のムーブの指定管理も先月の市議会でご承認いただきました。議決前の指定管理者検討会での審議では、今後に向けたご意見に併せて、ムーブの事業に対して、
・社会の変化の中で、常に新しい事業、必要な事業を検討、実行されようとしており、とても良い。
・限られた予算や人員の中で、大変よく取り組まれていると感じた。
と、評価していただいたことは、これまでのムーブの実績、職員の苦労が報われ嬉しく思いました。
指定管理の申請に当たっては、管理運営方針として、
①性別による固定的役割分担意識の解消
②働く場をはじめ様々な分野での女性のエンパワーメントの推進
③次世代育成の視点を重視
④男性の視点からの男女共同参画の推進
⑤女性に対する暴力等人権侵害行為の根絶
⑥情報の収集・発信の充実
⑦市民の自主的な活動の支援
の7つの柱を提案させていただきました。
これらの指針の背景には、これまで20年間のムーブの実績があります。その実績を踏まえて、過去の実績に甘えることなく、常にそれぞれの時代や社会の課題に向けて職員が取り組んできたチャレンジ精神が脈々と息づいています。「ローマは1日にして成らず」です。個々の具体例は、別の機会にお話していこうと思っています。
今回の申請に当たり、ムーブを運営する(公財)アジア女性交流・研究フォーラム(以下、フォーラム)で開発してきた「女子学生のためのキャリア形成プログラム」やフォーラムで養成した「デートDV予防教育ファシリテーター」のフォローアップを、これからはムーブの事業として実施することを提案しました。これは、女性のためのエンパワーメント事業やDV相談を第一線の現場で実施しているムーブが行うことで、さらに現場感覚に根ざした事業に発展させていこうとするものです。
また、ムーブを運営するフォーラムは、ジェンダー平等、女性のエンパワーメントを目指して、アジア地域を中心とした国際的な交流・研究活動を実施しています。これまで日本の男女共同参画政策は、1975年の国際女性年以降は、国連施策が指針となって国際的な影響を受けながら進んできました。さらに、現在のグローバル化が進展する社会では、私達の生活そのものが国際的な影響を受けながら営まれています。従って、国際的視点を持つことで見えてくる課題の解決策があると思っています。これからは、フォーラムの事業も含め、ムーブでも国際的な視点を視野に入れた取り組みを行ってまいりたいと思っています。
新年を迎えて、今年度の事業も目白押しです。
是非、ムーブまで足をお運びください。

北九州市から3人の方が福岡県男女共同参画表彰を受賞

11月28日に、第14回福岡県男女共同参画表彰の表彰式が開催されました。6人の受賞者のうち3人が北九州市で活躍する女性でした。北九州市には元気に活躍されている女性がたくさんいます。
「社会における女性の活躍推進部門」では土井智子さん、「困難な状況にある女性の自立支援部門」ではDV防止北九州メープルリーフの会、「女性の先駆的活動部門」では梅の里工房が受賞されました。
3人ともムーブの事業でお世話になった方々なので、大変嬉しいニュースで、喜んでいます。
「社会における女性の活躍推進部門」の土井智子さんは、北九州市女性団体連絡会議の会長、副会長、理事を歴任。民生委員・児童委員など、これまでにさまざまな活動をされてこられました。特に、北九州市女性団体連絡会議の会長の時代にはムーブフェスタ実行委員長を2009年~2012年までの4年間務めていただきました。期間中は毎日のようにムーブに通っていただき、ムーブフェスタを盛り上げていただきました。
DV防止北九州メープルリーフの会は、ムーブフェスタの市民企画事業でのジェンダー問題を主題としたシンポジュウム・講演会等の実施や、ムーブのジェンダー問題調査・研究支援事業で「デートDVの実態及び意識に関するアンケート調査」を実施していただきました。その結果、若年層のDV対策として早期の予防教育の必要性を痛感し、以来、市内の大学・高校等において、デートDV予防教室を開催していただいています。
梅の里工房の代表の明石久実子さんには、昨年「シニア世代の女性の生き方」をテーマにしたムーブ・レディス映画祭の『もうヒトハナ、咲かそ』上映後実施した『いろどりカフェ』で、日頃の活動をお話ししていただきました。
参加された方々は、女性目線を活かした活動のお話に引き込まれ、また、会場で展示販売した「梅ちゃんシリーズ」の梅ドレッシングや梅ジャムなども、大好評でした。
写真は、表彰式の際に撮影したものです。
北九州市にはまだまだたくさんの活躍する女性たちがいます。今年度に引き続き、来年度も受賞して欲しいものです。

『スクール・セクハラ』って知ってますか。

国の「女性に対する暴力をなくす運動」(11月12日~25日)に連動してムーブでは11月25日に「女性への暴力ゼロ!ホットライン」を開設し、女性への暴力に関する相談を受けるとともに、毎年「女性への暴力ゼロ運動特別講座」を開催しています。
今年は「スクール・セクハラ」を取り上げ、NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワークの亀井明子さんに講演をしていただきます。
私が「スクール・セクハラ」という言葉を知ったのは、平成25年12月の亀井さんの講演会でした。
子どものころに受けたセクハラが、後々の人生に大変影響していること、学校現場では教師仲間は知っていても表に出にくいこと、また、セクハラの事実を把握していても、転勤してしまえばそのままになってしまうことがあると聞いて、衝撃を受けました。
また、法整備も含めて制度面で遅れている分野で、当面は、被害者支援の視点で、被害者が相談できる体制の充実が必要であると感じていました。
以来、ずっと気になっていましたが、平成26年に、池谷孝司著『スクールセクハラ』(幻冬社)が発行され、ムーブの書誌情報誌『カティング・エッジ』でも紹介書籍として取り上げました。亀井氏の書評の中から引用させていただきます。
本書から著者の3つのメッセージが読み取れる。1つ目は、教員が権力関係を利用して子どもに対して起こすセクハラ被害の実態がきわめて深刻だということ。2つ目は、最高責任者である学校長のセクハラに対する認識が極めて低いということ。3つ目は、被害者とその保護者は二次被害に苦しんでいるということである。…
多くの先生が、子どもたちの教育に懸命に取り組まれていると思います。ほんの一部の先生による「スクール・セクハラ」で、心に傷を持つ子どもたちが存在するのであれば残念なことです。
まだまだ「スクール・セクハラ」という言葉はそれほど広まっていませんが、子どもたちが被害にあっている現状を知り、皆さんとどう向き合っていけばよいのか一緒に考える機会にしたいと思っています。
講演会は、11月15日(日)13:00~15:00です。是非、ご参加ください。
平成27年度女性への暴力ゼロ特別講座 「知っていますか?“スクール・セクハラ”」はこちらから

ベトナム・カンボジア スタディツアーに参加して

9月初め、ベトナム・カンボジア スタディツアーに同行しました。20代前半の15人の若者たちと一緒のツアーでした。
ベトナムでは、ハイフォンとハノイを訪問。ハイフォン私立大学と九州国際大学の学生との交流事業、ハノイ女性連盟の訪問、TOTOハノイ工場訪問などを行いました。
年5~6%の経済成長率のベトナムは、活力溢れる国でした。バイクや自動車が、次から次に道に溢れてきます。3人乗り、4人乗りもあたり前。道路の横断は命がけです。路上屋台は歩道に張り付くように、道を占拠しています。徐々に、インフラ整備も進み、道路、空港整備が進んでいます。今、飛躍的に発展しています。
ベトナムは、戦後の日本がまだインフラ整備も十分ではなく、これから経済が成長していくという私の幼いころの日本を思い出させます。
次の目的地のカンボジアでは、2つの小学校と日本国際ボランティアセンターの支援で栄養菜園プロジェクトを実施している農村を訪問しました。
小学校では、学生たちが用意した縄跳び、折り紙、けん玉、ゴム鉄砲などで遊びました。国も、年齢も、言葉も違いますが、子どもたちは大学生と、夢中になって遊んでいました。私も、カンボジアの子どもたちの仲間に入れてもらって、私の幼い頃に遊んだ石蹴りで一緒に遊びました。
学校の図書室には本が少なく、九州国際大学の学生さんが絵本を贈る活動「BOOK TO READプロジェクト」を実施しています。校長先生のお話では、子どもたちは小学校は卒業するものの、半数は中学校を卒業せずに、工場や工事現場に働きに行くということです。
農村では、家を見せていただきましたが、家財道具はわずかで最小限の家財で生活されていました。我が家の無駄なものの多さを反省しました。
日本に比べて貧しさの残るベトナム、それよりももっと貧しいカンボジアでしたが、かえって、戦後の貧しい日本の時代に生まれ育った私にとっては、何が、本当の豊かさのなのか、考えてしまいました。
我が家にはいろいろなものが溢れています。街並みもきれいになっていますが、幼い頃の隣近所で助け合って生活していた時代と比べ、本当の豊かさとは何?と、考えるスタディツアーになりました。
このブログでは、スタディツアーで経験したことを書き尽くせません。興味がある方は、10月11日(日)14:00~15:30に、スタディツアー報告会を実施しますので、ご参加ください。

大学における性的マイノリティの学生支援

ムーブでは、北九州市の男女共同参画社会の形成の障害となっている問題をジェンダーの視点から掘り起こし、問題解決の糸口を探る「ジェンダー問題調査・研究支援事業」を実施しています。
平成26年度は、北九州市立大学教授の河嶋静代先生による調査・研究「性的マイノリティの学生支援における課題」を支援しました。そして、今年7月に調査・研究の報告会を開催しました。
当初は、「性的マイノリティに対する大学のサポート体制」と「性的マイノリティの学生サークル」についての調査・研究となっていましたが、是非、「全国の大学の実態を調べて欲しい」とお願いし、全国の大学や短大へのアンケート調査も合わせて行っていただくことができました。性的マイノリティに対する調査は全国でもほとんどないということです。
その結果、回答のあった大学241校のうち121校、約半数が性的マイノリティの学生から相談があったことが分かりました。相談内容は、「学生生活」「家族・友人、「就職、将来について」などとなっています。
しかし、「健康診断」「トイレ利用」「授業での名前の呼び方」「更衣室・シャワールームの利用」「通称名での学生証の発行」など特別の配慮をしている大学等があるものの、性的マイノリティの学生に対して、243校のうち161校、約7割が特別な配慮をしていないことが分かりました。
調査では、さらに、先駆的な大学での取組みを紹介しています。今後、これらの大学をロールモデルとして、他の大学等へと支援が広がっていくことを期待したいものです。
河嶋先生の所属する北九州市立大学では、既に、今年の4月から学生証や卒業証明書に通称名が使える制度を導入したということです。
ムーブでは、平成24年度、性的マイノリティの方からの相談を受けたことをきっかけに、対人援助者セミナーに「性的マイノリティ」を取り上げ、平成25年度は、当事者を交えての講演会を実施しました。
渋谷区では、今年4月、同性カップルをパートナーと証明する条例を施行するなどの動きもあります。
7月の調査・研究の報告会では、遠くは東京など市外からの参加者も多く、性的マイノリティに対する関心の深さを感じました。
報告会で、コメンテーターをしていただいた、元国際基督教大学のジェンダー研究センター長の田中かず子さんのコメント、「性的マイノリティは、マイノリティの問題だけでなく、マジョリティ側の問題でもある」と言われたことが印象に残っています。
マジョリティ側の理解を深めるため、これからも取り組んで行っていくことが必要だと考えています。
*「性的マイノリティ」とは、性別違和感がなく異性を愛する人が多数者であることに対し、LGBT(IQ)の人たちを総称して
使うことが多い。LGBTとは、英語のレズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランス
ジェンダー(Transgender)の頭文字である。
(平成26年度 ジェンダー問題調査・研究支援事業報告書P6より)
書誌情報誌『Cutting-Edge カティング・エッジ』について

皆さん、ムーブが発行している『Cutting-Edge カティング・エッジ』をご存知ですか。
ジェンダー問題解決のカギを提示する最前線の書誌情報誌と銘打って発行しています。2001年1月に創刊号を発行し、2015年6月までに54号を発行しました。
どのような趣旨で発行しているのか2009年3月発行の『Cutting-Edge 総集編版』の「はじめに」から引用させていただきます。
「・・・(略)・・・国内外における男女共同参画推進の動きや課題の変遷、またその時々の議論や研究および運動の成果は、本書を読むことで端的に掴むことができる構成になっています。」
「・・・(略)・・・情報および情報機器へのアクセスの男女格差の解消が女性のエンパワーメントの重要な戦略であるとの国際認識(1995年採択の北京行動綱領)を踏まえ、“Think Globally、Act Locally”すなわち男女共同参画社会の実現にむけて地球規模の視座に立った情報を北九州市から発信することを目指してまいりました。」
また、巻頭言、書誌情報とキーワード解説、ジェンダー・エッセイについては、
「未来を見通す目で男女共同参画の推進に毎回新しい風を吹き込む巻頭言、男女共同参画の推進を困難にする現実を切り取り、問題解決のカギを示す書評およびキーワード解説、しなやかな感性と冷徹な目で男女共同参画問題を読み解いてみせるジェンダー・エッセイ」と説明しています。
さて、私は、2013年6月10日発行の48号から発行に関わっています。できるだけ多くの方々に読んでいただきたいという職員の提案を受けて、デザインを刷新するとともにカラー版にしました。また、男女共同参画やジェンダーについてマンガを通して理解していただこうと、「マンガコーナー」を新設。「マンガーコーナー」は大好評です。おかげでこの『カティング・エッジ』はこれまで以上に多くの方々に手に取っていただいています。
発行にあわせ図書・情報室に特設コーナーを設置することで、『カティング・エッジ』で取り上げた本の貸出しも増えています。
巻頭言やジェンダー・エッセイのテーマを何にするのか、どなたに書いていただくのか、また、書誌情報に掲載する本は何にするのか、書評はどなたにお願いするのか、編集会議で議論します。
書評の本については、担当者を含めて日頃から、これはという本を各自が読み、提案します。そして、提案された本を編集委員全員が目を通して選びます。そして、この本であれば、この方に書評をお願いしようと考えるのも、楽しみな作業です。そして、書評が送られてきて、取り上げた本が的を射た選択であったことを確認できたときは、発行者冥利につきます。
今年の3月~5月に誌面に関するアンケート調査をいたしました。「今回初めて読みましたが大変、中身が充実している、よい書誌情報誌でした。特に書評に各本のキーワードの解説が載っていたのがよかったです。」「ジェンダー問題に特化している情報誌が少ないので、読むたびに勉強させてもらっています。基本的な内容も掲載していただけるともっとわかりやすい。」などの意見をいただきました。
これからも改善し、より皆さまに読まれる書誌情報誌にしていきたいと思っています。
皆さま、是非、読んでください。そして、ご意見をお寄せください。
※写真をクリックすると「カティング・エッジ」最新号のページに飛びます
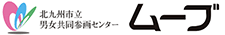



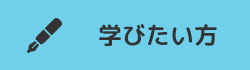
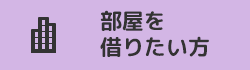
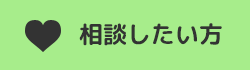
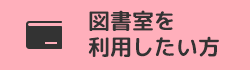

1.jpg)